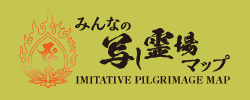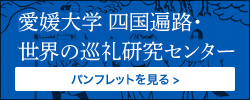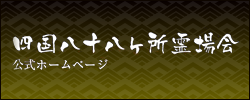愛媛大学ミュージアムで「遍路案内記の世界」展を開催しています【1月10日(土)まで】
愛媛大学ミュージアムで、「遍路案内記の世界」展を開催しています。
開館情報は、愛媛大学ミュージアムホームページで確認ください。
1 研究最前線
(1)カトリックにおける聖母マリア崇敬と巡礼(田島篤史)
(2)ロンドンのポプラー地区におけるキリスト教会と戦争記念碑(吉田正広)
(3)テレビがうつす四国遍路(中川未来)
(4)モートン・コレクション(胡 光)
(5)小松島市地蔵寺の総合調査(胡 光)
2 遍路案内記の世界
江戸時代は旅の時代です。参勤交代を行う武士だけでなく、許可を得て多くの庶民が旅に出ました。江戸時代の旅人が記した旅日記・紀行文や、旅人を誘う案内記を「道中記」と言います。このうち、四国遍路の日記を「遍路日記」、刊行された案内本を『遍路案内記』と呼び、両書を中心に、信仰と祈りの旅の姿を紹介します。新たに加わったモートン・コレクションをはじめ、センターが所蔵する様々な絵画や写真、書籍、古記録、歴史資料をご覧ください。
3 遍路のまなざし
四国遍路の原型は、僧が行った辺地修行に由来し、江戸時代までには、八十八の札所も誕生し、修行の辺路から巡礼の遍路へ変化して、多くの庶民が四国を巡るようになった。遍路の特徴は、円環型で終わりがなく、本堂の本尊のほかに大師堂の弘法大師を拝するところにある。江戸時代には、札所の中に神社も存在したが、明治維新によって寺院に統一された。
4 案内記の誕生
弘法大師に所縁の場所、奇跡や伝説の舞台などは神聖視され、聖地として多くの信仰と信者を生み出した。その最も大きなネットワークが四国遍路である。信者を誘うため、案内本や霊験譚が誕生する。貞享四年(一六八七)真念によって初めて『四国辺路道指南』が刊行されると、遍路ブームが起こり、上方では歌舞伎も上演された。
5 遍路の見た風景
藩=国だった江戸時代には、巡礼を理由として、パスポートである往来手形を手に旅に出た。四国遍路が盛んになると、日記や納経帳など聖地巡礼の記憶や記録が残されていった。信仰と旅情が交錯する生きた情報は、遍路文化の継承に大きく貢献した。今もなお、四国遍路と弘法大師信仰は拡大を続けている。
6 主な展示資料
オーストリア・奇跡のメダル、イギリス・ポプラ―の絵葉書、四国徧礼道指南、四国徧礼道中図、四国霊験奇応記、金毘羅道中記、西国三十三所観音霊場図会、四国霊験記図会、四国霊場大観、往来手形、納経帳、四国巡拝みちの日記、お遍路、画と文四国遍路
*本展覧会は、胡光センター長が指導した人文社会科学研究科の授業で、横井蒼大・森貞雄仁・渡邉裕人・大野瑞希・大森昴・加藤大晴が企画・解説にあたったものです。